世界陸上競技選手権大会とTDK
真の陸上世界一決定戦

世界のトップアスリートたちが競い、陸上世界一を決める世界陸上競技選手権大会。その歴史は、他の競技の世界選手権に比べて、それほど古くはありません。
世界陸上競技選手権大会以前は、世界中のトップアスリートたちがすべて集まる大会といえばオリンピックより 他にありませんでした。そこで、「世界のトップアスリートたちが全員参加して、真の陸上世界一を決める大会をやろう」という声が世界の陸上関係者の間で起こりました。このような気運の高まりの中、World Athletics (WA)*は、1978年プエルトリコで開いた評議委員会において「世界陸上競技選手権大会」を満場一致で可決。合わせて、第1回大会を、1983年8月、フィンランドのヘルシンキで開催することを決めたのです。
当初、この大会は4年に一度、オリンピックの前年に開かれていましたが、第3回の東京大会 (日本)以降、2年に一度、オリンピックの前年と翌年の隔年開催となりました。世界陸上競技選手権大会は現在まで18回に渡って世界各地で開催され、世界のトップアスリートたちが競い、全世界に熱い感動と興奮を 呼び起こしてきました。
TDKはこの世界陸上競技選手権大会を1983年の第1回ヘルシンキ大会からゼッケンスポンサーとして協賛してきました。そして2029年までオフィシャルパートナー活動を継続します。
世界陸上競技選手権大会の歴史
1983

第1回大会
ヘルシンキ (フィンランド)
- 参加国・地域:183
- 参加選手:1,335人
- 種目:41(男24、女17)
1987

第2回大会
ローマ(イタリア)
- 参加国・地域:157
- 参加選手:1,741人
- 種目:43(男24、女19)
1991

第3回大会
東京(日本)
- 参加国・地域:164
- 参加選手:1,705人
- 種目:43(男24、女19)
1993

第4回大会
シュツットガルト(ドイツ)
- 参加国・地域:187
- 参加選手:1,884人
- 種目:44(男24、女20)
1995

第5回大会
イエテボリ(スウェーデン)
- 参加国・地域:191
- 参加選手:1,959人
- 種目:44(男24、女20)
1997

第6回大会
アテネ(ギリシャ)
- 参加国・地域:198
- 参加選手:1,914人
- 種目:44(男24、女20)
1999

第7回大会
セビリア(スペイン)
- 参加国・地域:202
- 参加選手:1,854人
- 種目:46(男24、女22)
2001

第8回大会
エドモントン(カナダ)
- 参加国・地域:189
- 参加選手:2,000人
- 種目:46(男24、女22)
2003
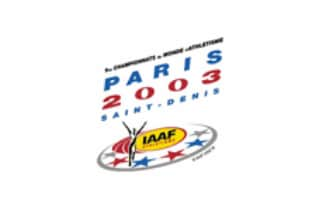
第9回大会
パリ(フランス)
- 参加国・地域:198
- 参加選手:1,679
- 種目:46(男24、女22)
2005

第10回大会
ヘルシンキ(フィンランド)
- 参加国・地域:196
- 参加選手:1891人
- 種目:47(男24、女23)
2007

第11回大会
大阪(日本)
- 参加国・地域:201
- 参加選手:1,930人
- 種目:47(男24、女23)
2009
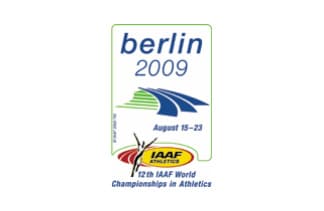
第12回大会
ベルリン(ドイツ)
- 参加国・地域:201
- 参加選手:1,984人
- 種目:47(男24、女23)
2011
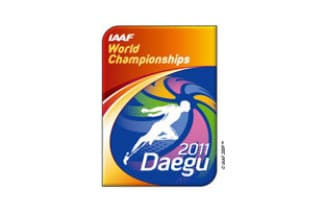
第13回大会
テグ(韓国)
- 参加国・地域:212
- 参加選手:3,500人
- 種目:47(男24、女23)
2013
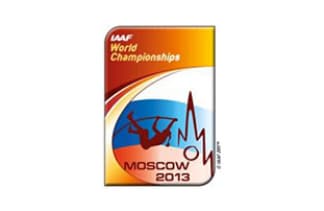
第14回大会
モスクワ(ロシア)
- 参加国・地域:212
- 参加選手:3,200人
- 種目:47(男24、女23)
2015
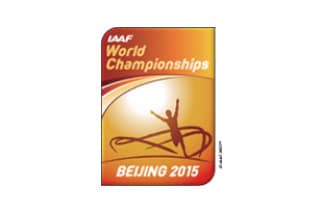
第15回大会
北京(中国)
- 参加国・地域:212
- 参加選手:3,200人
- 種目:47(男24、女23)
2017
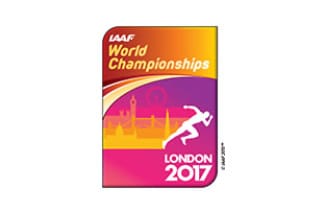
第16回大会
ロンドン(イギリス)
- 参加国・地域:205
- 参加選手:2,038人
- 種目:48(男24、女24)
2019

第17回大会
ドーハ(カタール)
- 参加国・地域:206
- 参加選手:1,772人
- 種目:49(男24、女24、混合1)
2022

第18回大会
オレゴン(アメリカ合衆国)
- 参加国・地域:179(+Athlete Refugee Team)
- 参加選手:1,705人
- 種目:49(男24、女24、混合1)
2023

第19回大会
ブダペスト(ハンガリー)
- 参加国・地域:195
- 参加選手:2,100人
- 種目:49(男24、女24、混合1)
2025

第20回大会
東京(日本)
- 参加国・地域:約210
- 参加選手:約2,000人
- 種目:49(男24、女24、混合1)
ヘルシンキ
(フィンランド)
・アメリカのカール・ルイスが100m、走り幅跳び、4×100mリレーで三冠達成。リレーでは37秒86の世界新記録を打ち立てる。
・アイルランドのイーモン・コグランが、5000mで後続に大差をつけ優勝。最後の直線コースに入る前にすでに勝利を確信しガッツポーズをみせる。
・この年負けなしだったフィンランドのティーナ・リラクは、この大会の槍投げ決勝では最初の5ラウンドまで2位に甘んじるも、最後の一投で70.82mの大投てきを放ち、逆転で金メダルを射止めて、母国の観衆を歓喜に沸かせた。
・女子マラソンのグレテ・ワイツが、後続にきっかり3分の大差をつけ、記念すべき第1回大会のタイトルを勝ち取った。これは、国際大会で彼女が手にした唯一の金メダルであると同時に、女子マラソン選手に与えられた最初の国際タイトルとなった。
ローマ(イタリア)
・ローマ大会400mハードル決勝で、アメリカのエドウィン・モーゼスが0.02秒の僅差で3人のメダリストを辛くも振り切り、大会新記録となる47秒46で優勝。その年のはじめに伝説的な連勝記録がストップしていた彼は、この大会で王座に返り咲く。
・10,000mの覇者、ケニアのポール・キプコエチがアフリカ人初の世界王者に。
・七種競技では、ジャッキー・ジョイナー=カーシーが終始レースを支配し、7128点の大会記録で優勝。彼女はその3日後、今度は走り幅跳びで、こちらも大会記録となる7.36mを叩き出し、もう一つの金メダルをさらった。
・走り高跳び決勝、世界女王ステフカ・コスタディノヴァは、2.04mであわや脱落しかけたが、3度目でようやくクリアし、バーの高さが2.06mとなった時点では2位。しかし、2回目でこれをクリアすると、その後、前人未踏の2.09mも2回目で成功させ、自身のもつ世界記録を更新して優勝。
・女子マラソンでは、ポルトガルのロザ・モタが、国際大会としては一二を争うほどの圧倒的なレース展開でライバルを寄せ付けず、2位を7分21秒も引き離す2時間25分17秒で圧勝。
東京(日本)
・走り幅跳びで、同胞のライバル、カール・ルイスと名勝負を繰り広げたアメリカのマイク・パウエルが、5度目の跳躍で世界新記録となる8.95mのビッグジャンプを見せ、ルイスに競り勝つ。他方のルイスは8.91mと、追い風参照記録ながら1968年にボブ・ビーモンが打ち立てた世界記録を上回るも、わずかに及ばす。
・4×400mリレーで、ハードルのクリス・アカブシと200mスペシャリスト、ジョン・レジスを擁するイギリス代表チームが欧州新記録をマークし、大本命のアメリカを破って優勝。
・マラソンの谷口浩美が母国日本でのレースを制し、日本中が歓喜に沸く。
・アメリカのグレッグ・フォスターが3大会連続で110mハードルの世界タイトルを手に。
・女子1500mで、ハシバ・ブールメルカが最後の直線でラストスパートを見せて勝利。アフリカ人女性初の世界タイトルを手にした。
・走り高跳びでは多くの番狂わせが起きるものだが、ハイケ・ヘンケルの場合は例外。1991年の決勝はパーフェクトだった。勝負を決めた2.05mを含め、一度として失敗することなく、女王の貫禄をみせつけた。
・この年、個人種目で負けなしだったマリー=ジョゼ・ペレクは、東京でも400mを制し、記憶に残る無敗シーズンを圧勝で締めくくった。
・ジャマイカの女性スプリンターが個人種目でメジャータイトルを独占するようになる以前、この国に最初の金メダルをもたらしたのは東京での4×100mリレーだった。100mと200mで銅メダルをとったマリーン・オッティが、アンカーとして圧巻の走りを見せ、41秒94でチームを勝利に導いた。
シュツットガルト(ドイツ)
・イギリスのコリン・ジャクソンが110mハードルで世界新記録を樹立。
・十種競技全米予選で棒高跳びに失敗しアメリカのオリンピック代表入りを逃す失意から1年後、ダン・オブライエンが世界王座を奪還し、雪辱を果たす。
・1993年の女子100m決勝は、大会史上もっとも僅差のレースだった。10秒82で優勝したゲイル・ディバースの2位との差はわずか1000分の1秒。ディバースは100mハードルでも金を獲得。
・女子400mハードルでは、サリー・ガネルが最大のライバルサンドラ・ファーマー=パトリックとの大接戦の末、52秒74の世界新記録で優勝。両者とも以前の大会記録を上回った。
イエテボリ(スウェーデン)
・アルジェリアのヌールディン・モルセリが、1500mで自身3度目となる世界王者に。
・イギリスのジョナサン・エドワーズが三段跳びの世界記録を2度更新。1度目は18.16m、2度目はさらに記録を伸ばし、18.29mを叩き出す。この記録はいまだ破られていない。
・自宅の火災で大やけどを負ったアナ・フィデリア・キロットは、その2年半後、この大会で復活を遂げる。800mで世界一となり、自身初の世界タイトルを勝ち取った。
・前回大会につづき、女子400mハードル決勝の1位と2位が世界記録をマーク。キム・バッテンとトーニャ・ビュフォード=ベイリーのライバル対決は、0.01秒の僅差で、52秒61のバッテンに軍配が上がった。
・前々回の1991年大会で最下位に沈んだ七種競技のガーダ・シュアーが、4年後のイエテボリ大会で雪辱を果たし、世界タイトルを手にした最初のシリア人となった。
アテネ(ギリシャ)
・棒高跳びのレジェンド、セルゲイ・ブブカが、6大会連続で世界王者に。
・モロッコのヒシャム・エルゲルージが、前年のオリンピック決勝での転倒の悪夢から復活、1500mで自身初となる世界タイトルを勝ち取る。
・若干15歳で銅メダルを獲得してから4年、1997年に、当時まだ19歳だったサリー・バルソシオが10000m で優勝し、ケニア人女性で初めて世界タイトルを手にした。
・女子5000mで、ルーマニアのガブリエラ・サボーが、ロベルタ・ブリュネとフェルナンダ・リベイロとの接戦を制し、自身が獲得した三つの世界タイトルのうちの最初のタイトルを手にした。
・金メダル獲得に向けた三つ巴の戦い で、ノルウェーのハンネ・ハウグランドが最終的に1.99mに成功、走り高跳び世界タイトルを獲得。
セビリア(スペイン)
・エチオピアのハイレ・ゲブレセラシェが、4大会連続で10,000mを制覇。
・アメリカのマイケル・ジョンソンが43秒18で400m世界記録を破り、個人種目で6つ目となる世界タイトルを獲得。
・デンマークのウィルソン・キプケテルが、ヘゼキエル・セペングとの接戦の末、3大会連続で800mを制す。
・アメリカの女子棒高跳びのパイオニア、ステーシー・ドラギラが、女子では初めてとなる屋外大会の世界タイトルで、4.60mの世界記録を打ち立てて優勝。
・ケガで前シーズンを丸々棒に振ったキャシー・フリーマンは、1999年に復帰すると、400mでシーズン無敗の貫禄をみせつけ、セビリア大会で世界女王の座をほしいままにした。
・マイケル・ジョンソン(男子400m)に贈呈
エドモントン(カナダ)
・走り幅跳びのイバン・ペドロソ(キューバ)が、自身4度目となる世界王者に。
・槍投げのヤン・ゼレズニーが92.80mの大会新で、3度目となる世界タイトル獲得。
・円盤投げのラルス・リーデル(ドイツ)が、69.72mの大会新記録で大会5度目の優勝を果たす。
・前年のオリンピック男子マラソン王者、エチオピアのゲザハン・アベラが、ケニアのサイモン・ビウォットと接戦の末、1秒の差で逃げ切り優勝。
・前回銀メダルに終わった走り幅跳びのフィオナ・メイが、2位と1センチの差で辛くも勝利、6年ぶりに世界女王に返り咲いた。
・オリンピックでの歴史的勝利から9年、エチオピアのデラルツ・ツルが2位と0.04秒の僅差で10,000mを制した。
パリ(フランス)
・5000mで、当時18歳の新星エリウド・キプチョゲが、1500mの覇者ヒシャム・エルゲルージと10,000mの王者ケネニサ・ベケレを相手に息詰まる激戦を繰り広げ、大金星をあげる。
・アメリカのアレン・ジョンソンが、110mハードルで、自身4度目となる世界タイトルを獲得。
・ポーランドのロベルト・コジェニョフスキが、50km競歩で最初の公式世界記録を樹立し、同種目で自身3度目となる世界タイトルを勝ち取る。
・七種競技で、若干20歳のカロリナ・クリュフトが大躍進を果たし自己ベストを300点以上も上回る7000点の大台に乗せ、優勝を果たした。
・七種競技のスペシャリスト、ユニス・バルベルは、本業では銀に終わるも、その後出場した走り幅跳びで優勝して雪辱を果たす。この巻き返しに母国の観衆も歓喜に沸いた。
・女子4×100mリレーで、クリスティーン・アーロンがアンカーを務めたフランスチームがホームで劇的な優勝を果たし、スタジアムが熱狂の渦と化す。
・ジェファーソン・ペレス(男子20km競歩)に贈呈
・ロベルト・コジェニョフスキ(男子50km競歩)に贈呈
ヘルシンキ(フィンランド)
・円盤投げで、リトアニアのウィルギリウス・アレクナが、最終ラウンドで大会記録を破る70.17mを叩き出してトップに返り咲き、自身4度目の世界タイトルを獲得。
・土砂降りの雨のなか、アメリカのバーショーン・ジャクソンが自己ベストを上回る47秒30で、400mハードルを制する。
・ドカス・インジクルは、女子3000m障害走の記念すべき初の国際レースで優勝するとともに、母国ウガンダに初の世界タイトルをもたらすという歴史に残る偉業を成し遂げた。
・エチオピアのティルネシュ・ディババは、世界陸上で5000mと10,000mの二冠を達成した最初の女性アスリートとなった。
・女子槍投げで、キューバのオスレイディス・メネンデスが世界記録を破る71.70mをマーク、4年ぶりに女王の座に返り咲く 。
大阪(日本)
・走り幅跳びのイルビング・サラディノ(パナマ)が、アンドリュー・ハウとの息詰まるバトルの末、最後の最後に逆転して優勝。
・エクアドルのジェファーソン・ペレスが、自身3度目となる20km競歩世界タイトルを獲得。
・アメリカのジェレミー・ウォリナーが、43秒45の歴代4番目のタイムで、2大会連続400mを制覇。
・110mハードルで、第9レーンの中国リュウ・ショウが優勝。
・絶頂期にあり勢いに乗っていたアリソン・フェリックスが、後続に大会史上一二を争う大差をつけて200mのタイトルを貫禄で守る。さらに、4×100m、4×400mリレーでも金メダルをさらい、後者では48秒01という圧巻のスプリットをマークした。
・オーストラリアのヤナ・ピットマンは、出産後わずか9か月で、自身2度目となる400mハードルの世界タイトルを手にした。
ベルリン(ドイツ)
・2008年のオリンピックで100m、200m、4×100mと総なめにしたウサイン・ボルトが、ベルリン大会でもこれら全種目で世界新記録を叩き出し、三冠をさらう。
・エチオピアのケネニサ・ベケレが、5000mと10,000mの二冠を達成。10,000mでは大会新記録を樹立。
・女子走り高跳び決勝で、スタジアム中が自国のアリアネ・フリードリヒを応援するなか、ブランカ・ブラシッチがフリードリヒとの息詰まる対決を制し、世界タイトルを死守。
・女子槍投げで、37歳のベテラン、シュテフィ・ネリウスが自身最後となる大会出場、母国ドイツで有終の美を飾った。
・ウサイン・ボルト(男子100m/200m)に贈呈
テグ(韓国)
・日本の室伏広治が、ハンマー投げで2位と6センチの僅差で金メダル。
・走り幅跳びで、アメリカのドワイト・フィリップスが大会4度目の優勝を飾る。奇しくも、ゼッケン番号「1111」が勝利を予言。
・女子砲丸投げで、ニュージーランドのバレリー・アダムズが大会新記録と自己ベストとなる21.24mをマークし、大会3度目となる優勝を果たした。
・多くのアスリートが「デイリープログラムの呪い」(cover curse)にかかり、不振に陥るなか、100mハードルのサリー・ピアソンはこのいやな流れを撥ねのけ、大会新記録で鮮烈な勝利を収めた。
・N.カーター/M.フレーター/ ヨハン・ブレイク/ウサイン・ボルト(男子4×100mR)に贈呈
モスクワ(ロシア)
・ロバート・ハルティング(ドイツ)が、3度目となる世界タイトルを獲得。
・前年のオリンピックで2個の金メダルを獲得したイギリスのモハメド・ファラーが、世界陸上モスクワ大会長距離で二冠を達成。
・ジャマイカのシェリー・アン・フレイザー・プライスが100m、200m、4×100mリレーを制覇し、三冠をさらった。
・メジャー大会では6度の銀に甘んじていた槍投げのクリスティーナ・オーバークフォル(ドイツ)が、ついに悲願の金メダルを獲得。
北京(中国)
・三段跳びで、アメリカのクリスチャン・テイラーが歴代2番目の記録となる18.21mで優勝。
・3000m障害走のエゼキエル・ケンボイ(ケニア)が、自身4度目となる世界タイトルを獲得。このレースでは1位から4位までをケニア勢が独占。
・十種競技のアシュトン・イートンが、自身のもつ世界記録を更新する9045点で優勝。その内400mでは世界新となる45秒00をマーク。
・ダフネ・シパーズが、エレイン・トンプソン=ヘラーとの抜きつ抜かれつの大接戦の末、大会新と欧州新となる21秒63で200mを制す。
・女子ハンマー投げのアニタ・ヴォダルチクが、80.85mの大会新記録で、自身の四つの世界タイトルのうちの三つ目を獲得――80メートルの大台突破は、国際大会では初。
・アシュトン・イートン(男子十種競技)に贈呈
ロンドン(イギリス)
・4×400mリレーで、人口わずか150万の小国トリニダードトバゴが 、大本命のアメリカを破る大金星をあげる。
・チェコの槍投げバルボラ・シュポタコバが、最初の金メダル獲得から10年後、36歳で3度目のタイトルを獲得。
・走り幅跳びのブリトニー・リース(アメリカ)が、2位と2センチの僅差で優勝、自身4度目の世界タイトル、8個目の金メダルを手に入れた。
ドーハ(カタール)
・男子砲丸投げでハイレベルの大激戦が繰り広げられる――まずトーマス・ウォルシュが大会新記録、歴代タイ記録となる22.90mでリードして、決勝まで暫定1位をキープ。ところが、ジョー・コバックスが最終ラウンドで22.91mを叩き出して逆転勝利。次いで、ウォルシュと並ぶ22.90mをマークしたライアン・クルーザーは、わずか1センチ及ばず金を逃すも、カウントバック で銀メダル獲得。
・ケガから復帰したケニアのコンセスラス・キプルトが、2位と0.01秒の僅差で、3000m 障害走を制する。
・ケガから復帰した走り高跳びのムタズ・エサ・バルシムが、自国開催の大会で王座を奪還、観衆をおおいに沸かせる。
・オランダの長距離走者シファン・ハッサンが、1500mと10,000mというユニークな二冠を果たす。
・アメリカのダリラ・ムハンマドが、同胞のライバル、シドニー・マクラフリンとの接戦の末、52秒16の世界新記録で400mハードルを制した。
・コートニー・オコロ/アリソン・フェリックス/マイケル・チェリー/ウィルバート・ロンドン(混合4x400mR)に贈呈
オレゴン(アメリカ合衆国)
・ハンマー投げのパウエル・ファイデク(ポーランド)が、大会5度目の優勝を果たす。
・棒高跳びのアルマンド・デュプランティスが自身のもつ世界記録を塗り替える6.21mで優勝。オレゴン大会の有終の美を飾る。
・女子100mハードル準決勝で、ナイジェリアのトビ・アムサンが世界記録を破る12秒12を叩き出した。彼女はその日の夜の決勝で、これが決してまぐれでなかったことを証明―――わずかに追い風ながら、昼の記録をさらに上回る12秒06をマークして優勝。
・女子400mハードルでは、シドニー・マクラフリンが圧倒的な強さでレースを支配、50秒68で世界記録を打ち破る。
・2度のオリンピック400mの覇者ショーナ・ミラー=ウイボが、5度目の大会出場で、ついに念願の屋外大会世界タイトルを手に。
・三段跳びのジュリマール・ロハス(ベネズエラ)が、2位に50センチ以上の大差をつける15.47mのビッグジャンプで、3大会連続優勝を果たす。
・アルマンド・デュプランティス(男子棒高跳び)に贈呈




