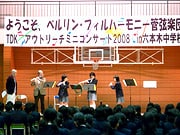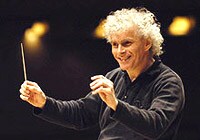TDKオーケストラコンサート2008
2001年より、世界の著名オーケストラの日本公演に協賛しているTDKオーケストラコンサート。2008年は、世界を代表するオーケストラとして君臨する「ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」と世界最高峰の指揮者サー・サイモン・ラトル氏の3年ぶりの来日コンサートに協賛。今回は、ラトル氏にとっての新境地であるブラームスの交響曲を全曲演奏するというプログラムで、全世界から注目される公演となりました。11月26日には、公開リハーサルに音楽を学んでいる18歳以上の学生200名をご招待。指揮者とオーケストラが楽曲を仕上げていく様子を鑑賞いただきました。 TDKでは、今後も世界的なオーケストラの日本公演への協賛を継続していく予定です。
公開リハーサル
11月26日(水)、本公演に先立って行われた「公開リハーサル」に、音楽を勉強している18歳以上の学生の方200名を抽選でご招待しました。リハーサルを鑑賞していた学生たちは、ラフな服装の楽団員が本番さながらの演奏に集中する姿や、指揮者ラトル氏が楽団メンバーと念入りに打合せする姿や楽団員同士が打ち合わせしながら音あわせをする様子など、普段目にすることのない音作りの過程を見聞きでき、とても貴重な体験となったようです。
「公開リハーサル」を鑑賞された学生の感想(会場でのアンケートより)
「世界最高峰の音を、本番は一度きりしか聴けないのに、何度も聴けて、しかも違う音色で。リハーサルの一部始終を見られたこと、感動しました。」(専門学校生:女性)
「オーケストラのリハーサルという普段めったに聴けないものを目の前で聴けて、指揮者が注意した前と後での微妙な違いを発見するたびに、今までに味わったことのない感動がありました。」(大学生:女性)
「オーケストラのメンバーが綿密にコンタクトを取っている(言葉を交わす)のが印象的でした。一人ひとりの技術はすごいと思いましたが、和音を作ったときのホールを包み込むような響きの美しさも感激しました」(大学院生:男性)
「曲を通すのではなく、各楽器への指示などをしている風景が見られ、とても興味深かった。何度も同じところを演奏することで、団員の演奏がひとつにまとまっていき、より流れがなめらかに、そしてメリハリがついた音楽になっていくように感じた」(大学生:女性)
「同じフレーズでも拍の感じ方やブレスで大きく印象が変わることなど、大変勉強になりました。細かい箇所でも音程や和音に気を遣うことの難しさをあらためて感じました」(短大生:女性)
アウトリーチミニコンサート
11月27日(木)、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の木管楽器のメンバー5名が港区立六本木中学校(東京都)を訪れました。楽団メンバーたちは技巧を凝らした演奏を5曲披露し、体育館に集まった生徒たち(約200名)は耳を澄ませて聴き入っていました。六本木中学校の吹奏楽部員によるフルート三重奏には、ベルリン・フィルの首席フルート奏者のアンドレアス・ブラウ氏が飛び入りで演奏に加わりました。一緒に演奏した生徒たちは「プロと一緒に演奏できとても感動しました。」、「自分たちよりも音がやさしくて、音の出し方が勉強になった。」などの感想が寄せられ、とても貴重な体験となった様子でした。また、生徒全員による合唱「ふるさと」を聞いた楽団員からは「日本の歌の合唱を聞いたのは初めて。とてもすばらしい。」といった感想が聞かれ、和やかな交流の場となりました。
公演概要
| 名称 | TDKオーケストラコンサート2008 |
|---|---|
| 主催/招聘/制作 | フジテレビジョン * 川崎/岡山の主催は下記 |
| 特別協賛 | TDK株式会社 |
| 出演 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 音楽監督・指揮 | サイモン・ラトル |
| 2008年11月23日(日) 午後4時開演 ミューザ川崎シンフォニーホール | |
|---|---|
| ハイドン | 交響曲第92番 ト長調 Hob.I92《オックスフォード》 |
| マーラー | リュッケルトの詩による5つの歌 ソリスト歌手(Ms):マグダレナ・コジェナー |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番 へ長調 作品68《田園》 |
*【主催】ミューザ川崎シンフォニーホール(川崎市文化財団グループ)
| 2008年11月25日(火) 午後7時開演 サントリーホール | |
|---|---|
| ブラームス | 交響曲第1番 ハ短調 作品68 |
| 交響曲第2番 ニ長調 作品73 | |
| 2008年11月26日(水) 午後7時開演 サントリーホール | |
|---|---|
| ブラームス | 交響曲第3番 へ長調 作品90 |
| 交響曲第4番 ホ短調 作品98 | |
| 2008年11月27日(木) 午後7時開演 サントリーホール | |
|---|---|
| ハイドン | 交響曲第92番 ト長調 Hob.I92《オックスフォード》 |
| マーラー | リュッケルトの詩による5つの歌 ソリスト歌手(Ms):マグダレナ・コジェナー |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番 へ長調 作品68《田園》 |
| 2008年11月29日(土) 午後2時開演 ザ・シンフォニーホール | |
|---|---|
| ハイドン | 交響曲第92番 ト長調 Hob.I92《オックスフォード》 |
| マーラー | リュッケルトの詩による5つの歌 ソリスト歌手(Ms):マグダレナ・コジェナー |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番 へ長調 作品68《田園》 |
| 2008年11月30日(日) 午後2時開演 兵庫県立芸術文化センターKOBELCOホール | |
|---|---|
| ブラームス | 交響曲第1番 ハ短調 作品68 |
| 交響曲第2番 ニ長調 作品73 | |
| 2008年12月1日(月) 午後7時開演 岡山シンフォニーホール | |
|---|---|
| ブラームス | 交響曲第3番 へ長調 作品90 |
| 交響曲第4番 ホ短調 作品98 | |
*【主催】ミューザ川崎シンフォニーホール(川崎市文化財団グループ)
出演者の紹介
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
(C)Andreas Knapp
ベンヤミン・ピルゼの楽団から独立した54人の楽員に新たに6名が加わり、1882年5月1日に発足。当初は常任指揮者をおかず、演奏活動を続けていたが、1887年にハンス・フォン・ビューローが初代常任指揮者に就任し、たった5年の舵取りで、ベルリン・フィルの名前と演奏水準を著しく向上させた。1895年から1922年まではアルトゥール・ニキシュの時代。ニキシュは多彩なレパートリーの基礎を作り、彼の指揮の下、オーケストラは国際的地位を獲得。共演を望んだ大物ソリストたちがこぞってベルリンを訪れたという。
1922年からはヴィルヘルム・フルトヴェングラーが常任指揮者を努め、短期間のうちにオーケストラを掌握し精力的な活動を展開。そのコンビネーションは、演奏史上でも際立った存在であったが、第2次世界大戦により活動が制約された上、戦後、彼が演奏を禁止されたことにより、ベルリン・フィルは危機的な状況を迎える。1947年にフルトヴェングラーが楽団に復帰。オーケストラも復興へと向い、1955年に初のアメリカ・ツアーが企画されたが、その前年、フルトヴェングラーが死去。ツアーは、ヘルベルト・フォン・カラヤンの手にゆだねられた。
翌1956年、カラヤンが終身指揮者兼芸術監督に就任。以後33年にわたって、カラヤン/ベルリン・フィルは数多くのレコーディングを通じて世界的名声を確立。音楽産業などに大きな影響を与えるとともに、西ベルリンという特殊な都市において「西側」の文化的地位を誇示する象徴的存在となった。1963年には、あらたな本拠であるフィルハーモニー(ハンス・シャロウン設計)が完成。1967年からはザルツブルク・イースター音楽祭に参加し、オペラにも進出。また、若い才能ある演奏家にトップクラスのオーケストラとの実地体験の機会を与えるため、ベルリン・フィル・オーケストラ・アカデミーも創設された。カラヤンは、亡くなる直前の1989年4月に辞任。
東西ドイツが統一された1990年にクラウディオ・アバドが首席指揮者・芸術監督に就任。メンバーの若返りが進み、オーケストラの柔軟性にも磨きがかかった。そして、2002年秋には、サイモン・ラトルが首席指揮者・芸術監督に迎えられ、現在に至る。ラトルとの来日公演は、2004年、2005年に続き、今回が3回目。
サイモン・ラトル(指揮)
(C)Berliner Philharmoniker
英国のリヴァプール生まれ。幼少の頃より打楽器とピアノを始め、ロンドンの王立音楽院に入学して指揮と打楽器を学ぶ。1974年、ジョン・プレイヤー国際指揮者コンクールで優勝し注目を集め、その後ボーンマス交響楽団の副指揮者を務めるなど、主にイギリスのオーケストラとの仕事を通じて指揮者としての経験を積む。1979年にロサンゼルス・フィルを振ってアメリカデビュー。
1980年、バーミンガム市交響楽団(CBSO)の首席指揮者に任命され、1990年秋から辞任する98年夏までは同楽団の音楽監督を務めた。その間、一貫して芸術的に興味深いプロジェクトを展開、また数多くの優れた録音により、CBSOは国際的なオーケストラへと躍進、演奏旅行も盛んになった。1994年、彼の著しい功績が称えられナイトの称号を授与され、「SIR(サー)」の敬称で呼ばれる。
CBSOでの活動と並行して、アメリカとヨーロッパを代表するオーケストラを指揮。なかでもボストン交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団およびウィーン・フィルとは長年にわたり共演を重ねている。また、古楽器オーケストラのエイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団との関係も深く、オペラの分野での活動にも早くから取り組んでいた。
ベルリン・フィルには1987年11月、マーラーの交響曲第6番を振って初登場。以来定期的に指揮台に立って様々な作曲者たちの作品を指揮し、その余りあるほどの力量で多くの楽員の信任を得、2002年9月、楽壇の最高峰とも呼べる同楽団首席指揮者および芸術監督のポストに就任した。現在、ベルリンでの忙しい演奏会スケジュールをこなすと同時に、両者は広く公演旅行を行ない、その数々の録音と先駆的な教育プロジェクトで多くの賞を受賞している。 また、ベルリン・フィルが主役となり、オーケストラ・コンサートのほか、オペラ上演時にはオーケストラ・ピットに入るザルツブルク・イースター音楽祭では芸術監督を務め、多大な成果を収めつつある。2007年、サイモン・ラトルとベルリン・フィルは、芸術的な楽団としては初めての名誉を授かり、ユニセフ親善大使に任命された。